しのぶれど(2)
- すずりもん
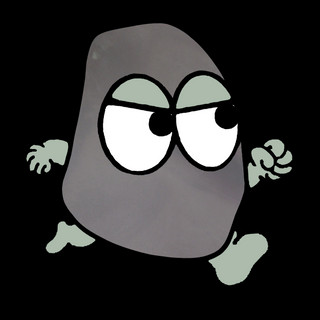
- 2025年2月21日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年3月28日
「ズキン」―千早と詩暢がすれ違った場所―
すっかり思い違いをしていた。千早と詩暢がすれ違ったこの場面である。
![末次由紀著『ちはやふる] 四 講談社 109頁より](https://static.wixstatic.com/media/47952e_dc23e8b8c08e432f8c3416463bb247c4~mv2.jpg/v1/fill/w_619,h_1000,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/47952e_dc23e8b8c08e432f8c3416463bb247c4~mv2.jpg)
ブログ主は、千早と詩暢がすれ違ったのは楼門へ向かう階段、つまり下の画像の階段だと思い込んでいた。

書き手は細かな所まで描いているのだから、もっと注意して読み進めるべきだったと反省しきりである。
上に添付したコミックのコマの左下に狛犬が描かれているが、楼門の階段付近に狛犬はいない。そばに狛犬が置かれている階段は楼門を抜けた先にある。
楼門への階段を上り切ると、まさに真っ赤な門が眼前に現れる。改めて見てもこの存在感は圧倒的だ。

楼門をくぐり抜けると広々とした風景が現れる。正面に見えるのが外拝殿で、外拝殿の前に階段があるのが分かるだろう。

外拝殿前の階段付近の画像が下である。2体の狛犬が見える。

つまり、千早と詩暢がすれ違ったのは楼門をくぐり抜けた先の外拝殿へ通じる階段、ちょうどこの階段だったというわけだ。
こちらには確かに狛犬もいる。千早と詩暢がすれ違ったのが楼門に向かって上る階段だと思い込んでいたときには、その広さに対して2人の位置関係がだいぶ近いように感じてはいた。が、それも演出的な描写なのだろうくらいに決めてかかっていた。
ブログ主は実際に外拝殿に通じるこの階段を登ったことがある。こちら階段は楼門前の階段に比べたらかなり幅が狭いので2人の位置関係もうなずける。勝手に誤解していた上に、これだけ大きく描かれた狛犬や背景描写を見逃すとは我ながらずさんな読者だとしか言いようがない。作者に申し訳ない限りだ。
当該のコマと外拝殿前の階段付近の画像をもう一度比べてみよう。


千早と詩暢がすれ違ったのは確かにこの階段だったようだ。
ということで一件落着―と言いたいところではあるが、実はもうひとつこの記事の記述で誤っている点がある。すでに拙文を読みながらお気づきになっている方もいたかと思う。
誤っている点というのは、この記事で「狛犬」と呼んてきた像のことだ。
ここまでの文で何度か「狛犬」という言葉を使ってきたが、正確な名称としては阿形と吽形、あるいは獅子と狛犬と言わなければならない。下図が吽形・狛犬と阿形・獅子。

左の口を閉じていて角のある方が吽形・狛犬,右の口を開いている方が阿形・獅子だ。どちらも伝説の生き物で、悪霊や邪気から本殿を守護する役割を担っている。
「狛犬」と呼んできた像についての誤りがあると言ったのは、「狛犬」という呼称が誤っていたからかと言えば、そういうわけではではない。
画像中の像は小さくしか映っていないので分かりにくいかもしれないが、近江神宮の外拝殿前の階段に安置されている像は両方とも口を開いている。では両方とも獅子なのかというと、それもいささか不思議な気がする。それもそのはず、本記事で「狛犬」と呼んできたこれらの像は、吽形・狛犬、阿形・獅子の像ではないらしいのだ。
いわゆる「狛犬」と呼ばれる阿形・獅子の像ではないならば何なのか―と言えば、単なる「二対の唐獅子の像」ということだ。同神宮の正式な狛犬・獅子は別のところにあるそうだが、これについては通常目にできるものなのかは分からない。
ブログ主はこれらの獅子の像に似たものをしばしば目にしている。篆刻の石材である。手近にあったもので獅子の鈕のついたものを写真に撮ってみたのでご覧いただきたい。



ちなみに、篆刻とは書道の分野のひとつで石材に印を刻するものだ。その篆刻で使われる石材にはしばしば獅子の鈕がついている。鈕はもともとは紐を通してぶら下げたり、持ち手として使われる部分だが、現代では装飾的意味合いの方が強いかもしれない。印材は主に中国で採掘され、それにしばしば施される獅子鈕はまさに中国風の獅子の典型だ。外拝殿の階段付近にある獅子像と似ているように思うがどうだろう。
「狛犬」に触れたついでに、もう少し獅子や狛犬について書き留めておこうと思う。もっとも、これらについては調べてみればみるほど煩雑で、記述に誤りがあるかもしれないがご容赦いただきたい。
まずは「獅子」についてだが、これはオリエントの頃が発祥のようで、王の玉座の左右の据えられたライオンの像がもとになっているという。それが霊獣や守護獣に変遷し、中国や朝鮮半島で「獅子」として定着したというのは比較的広く周知されている通りだ。
「狛犬」については、それが我が国へ伝来したのは飛鳥時代にさかのぼる。当時の文化は中国や朝鮮半島から輸入されたものが多くを占めるが、「狛犬」という神獣の存在そのものは中国や朝鮮の習俗にはない。が、一説には、「狛犬」の名称は、「高麗(こま)犬」や「胡麻犬」から来ているという。つまり、「狛犬」と表記される像そのものは日本独自のものではあるが、その伝来をたどれば中国や朝鮮半島をの影響を少なからず受けたものであることは疑いないだろう。そして、「狛犬」は「犬」ではなく、「獅子」の一種なのだそうだ。この点については、「狛犬」が獅子が変化したものなのか、獅子から分岐したものなのか、あるいは別の霊獣などが獅子と融合したものなのか、さまざま推察されるところではあるが、ブログ主にはその詳細については判断がつきかねる。
あくまでブログ主の想像の域に留まるものに過ぎないが、日本に伝来した二種の霊獣である「獅子」と「狛犬」は、二対で安置される霊獣あるいは守護獣として定着する過程で、一方は口を開いた形態の「阿形・獅子」、もう一方は口を閉じて角をもった形態の「吽形・狛犬」といった個別の特徴も残しながらも、シンメトリーを高めながらどこかしら類似した二対の像としての造形が完成されていったのではないだろうか。
さて、近江神宮外拝殿前階段付近の二対の像については、「阿形・獅子」に似た像は見られるものの、「吽形・狛犬」らしき像がない。二対のいわゆる「狛犬」の形態を満たしていないのだ。実際、同神宮においてもこれらの像は、獅子・狛犬とは見なされていないそうだ。あえて呼ぶならば、それらの像は「二対の唐獅子の像」ということになるだろうということは既述のとおりである。詳しく解説されている方からの拝借だが、これらの像は大津市ロータリークラブと中国のそれとの親善活動として共同で奉納品だそうだ。とすれば、唐風(中国風)の獅子像が寄贈されたというのも合点がいく。本来であれば現地でこうしたことに気がつければ理想的なのかもしれない。が、一方で、ブログ主は境内の雰囲気を楽しむこともまた神社・神宮巡りの醍醐味と思っているから、詳細な事柄は予習や復習になってもいいかなという気持ちも強い。蘊蓄を楽しむもよし、空気を楽しむもよしと思っている。
今回の記事では、千早と詩暢が初めてすれ違った場所やその近くに安置された像について、ブログ主が誤って認識していた点などから少し話を押し広げながら記事を綴ってみた。
なお、冒頭に添付したコマは、詩暢が本コミックに初めて登場するシーンであり、また、のちにライバルとなる千早と詩暢がすれ違うというある意味運命的なひとコマでもある。次回はこの場面の前後のいくつかのコマを拾いながら詩暢の初登場の場面の描写や演出について見てみようと思う。
