「墨磨職人」、お役御免になる
- すずりもん
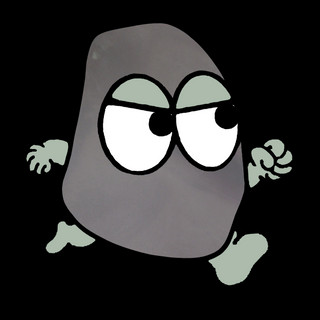
- 3月8日
- 読了時間: 7分
更新日:5月7日
書道に馴染みの薄い人にとって「墨」というと、容器の注ぎ口のからジューッと注いで使う液体の墨汁を思い浮かべる人が多いかもしれない。
あるいは学校の授業などで固形の墨の方を磨ったことがある人もいるだろう。硯の海に水を溜めてじゃぶじゃぶと磨ってはみたものの、さっぱり墨の色が濃くならなかった―などと言われるすこぶる評判の悪いあの固い墨だ。
固形墨が磨れないのは、ひつには書道セットなどについてくる墨がお飾り程度のものだからだ。上手く磨ればそれなりに濃くはなるが、磨り心地も発色も、そこはやはり値段相応としか言いようがない。
もうひとつは、磨る側の硯が良くないというのもある。学童用のセットにしばしばついてくるセラミックの硯は表面が滑るような感触で、墨の下りはあまり期待できる気がしない。書道セットの軽量化のために石の硯ではなくセラミックのそれになるのも分からなくもないが、あのセラミックの硯が墨をすることを想定しているかと言えば、正直甚だ怪しい気がする。
それから墨の磨り方が悪いというのもある。正しく使わなければ上手く性能を発揮できるべくもない。現代は文字を書くのに墨をする必要のない時代だから、墨を作るための道具の使い方が正しく伝わらなくなっていくのもある意味当然なのかもしれない。
用品の使い方と言えば、硯に水を差す水滴も次第に本来の扱い方を知る人が減りつつある。水滴に水を満たす方法も「こうした方が良い」というのはあるが、とりあえず水が入ればそこはまあいいとしよう。問題は水滴本来の使い方だ。結構な割合で醤油差しのようにじょろじょろと硯に水を注いでいるのを見かける。そんなようすを見ると刺身か寿司でも食っているのかと思わず苦笑してしまう。
2020年に奈良市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査センターで『令和2年度秋季特別展 ナニこれ!?―平城京出土の用途不明品―』という展示が行われた。用途不明品に特化した出土品の展示である。これが大変好評だったという。とうわけで翌々年には第2回目が開催されたそうだ。用途や使い方が伝承されなかった品物がそれだけ多いということだろう。と同時に、用途や使い方が分からなくなったら「これは何ぞ」と人々の関心が向くというところがまた興味深い。
情報が溢れているように見える現代ではある。しかし、情報が溢れているのは人の興味や関心が集まるものに対してである。水滴然り、人の興味・関心の集まらないものところには情報も集まらない。ニッチな世界にいる人ならすぐに分かるだろうが、情報化社会の情報は質も量も殊の外偏っていたりする。これだけ情報が氾濫していながら、ニッチな世界だと検索しても適当な情報が見当たらなかったり、あっても誤っていたりすることなど日常茶飯事だ。
ともあれ、本記事では墨の磨り方とか水滴の使い方とかを講釈しようという気はないので、興味のある人はその筋のサイトや動画などを検索されたい。ただし、ものによっては情報量が限られているし、説明が種々様々だったりすることもあるのでよく比較検討して適切な情報を見つける必要があるのでご注意のほど。
ところで、書道の師匠とか先生とか呼ばれる人たちが、皆、墨を磨っているのかと言えば案外そうでもない。大規模中央公募展で入賞・入選している作家たちでも市販の墨汁で間に合わせる人は多い。さすがに写経のような細字や仮名作品、篆刻の草稿を作るには墨を磨らないわけにはいかないだろうが、漢字や詩文書では作品次第で使う墨の量もかなり多くなるから、いかんせん手磨りでは追いつかないことも多い。しかも、わざわざ固形墨を磨らなくても市販の墨汁でそこそこいける、今はそういう時代だ。
確かに市販の墨汁の品質は格段に良くなった。が、一方で、色味やにじみの出方、運筆の滑らかさ、墨の伸びなどには限界もある。何より作品の構想に合うかと言えば、こればかりは難しい。市販品である限り、良くも悪くも最大公約数のような製品なのであって、自分独自の求めに合うことまで望むというのはさすがに無理だ。
そこで市販の墨液ではなくて固形墨を磨ろうということになることが少なくない。半紙程度なら手磨りでも十分だ。が、条幅などになると、枚数や墨の盛り方次第で相応の墨が必要になる。しかも、ようやく好みのにじみや色味が出たものの、途中で墨が無くなって再現できなくなったというのでは困る。そこで強力な味方になるのがこの「墨磨職人」だ。
遅ればせながら、この「墨磨職人」とは墨を磨る機械、つまり自動墨磨り機である。墨運堂から発売されている斯界では言わずと知れた大ヒット商品だ。ちなみに画像の「墨磨職人」は壊れてしまったものなので本来の姿ではない。実際のものは、横に置いているアームの部分が左の柱のところについている。柱が折れているさまが画像から分かるだろうか。


ブログ主がこの商品に最初にお目にかかったのは今から35年以上前、高校の書道教室で使われていたときだ。そのときは感心したというよりも、失礼だが無性に可笑しかったのを記憶している。ブログ主の頭の中には「墨を磨る」という所作はとても優雅で粋なものだという印象があった。だから、この「墨磨職人」のまさに機械的かつ無機質な動作が、「墨磨り」とイメージと相容れない何とも事務的で無粋な動作に見えて、それが主の目にはいたく滑稽に映ったのだ。
こんなことを書いたが「墨磨職人」を馬鹿にしようとか否定しようとという意図は微塵もない。それどころか、むしろ「墨磨職人」は今やブログ主にとって不可欠な道具である。とは言っても、墨磨りをすべて「墨磨職人」に任せているわけでもない。この「墨磨職人」が墨を磨っているとき、たいてい主もまた硯をで墨を磨っている。比較的安価な固形墨は「墨磨職人」に任せ、少し良い墨は硯を使って手で磨るのだ。そして、それらを混ぜながら墨の色味とかにじみを調整する。墨は機械磨りよりも手磨り墨の方が良い。理由はさして難しくもないのだが、それについてはいずれ気が向いたら語ろうと思う。
半月ほど前になるだろうか、いつものごとく「墨磨職人」を使っていたら突然アームが折れてしまった。かなり頑丈な造りなので正直折れたのには驚いた。しかし、考えてもみれば手に入れたのは30年近く前、そろそろ役目を終える時期だったのかもしれない。

「墨磨職人」は下の画像の円盤の部分で墨を磨る。昔はこの円盤がセラミック製だった。後になって天然石のものが発売されたので、追加購入して交換したのがこれだ。

画像でも薄っすらと円状に傷ができているのが画像でも確認できるかもしれないが、セラミック製だったときは使っているうちにみるみる削れてきてレコードの溝のようになり、やがては轍(わだち)のようになっていた。しかし、こちらはさすが天然石、耐久性はすこぶる良好だ。
ここ数か月はそれほど大量の墨を必要とする作品は作っていないので「墨磨職人」なしでも手磨りで特に不便なく過ごしている。けれど、時期が来れば「墨磨職人」の助太刀が必要になるときが来るだろう。そうなる前に新しい「墨磨職人」を迎え入れようかと検討中である。
少し調べてみたところ3万円前後するらしい。ブログ主がおよそ30年前に「墨磨職人」を購入したときよりはもっと安かったような気がする。25年以上も前に買ったときのことだから全く当てにならない記憶ではあるけれど。昨今は何から何まで物価が上がっているからそういう気がするだけかもしれない。あるいは、もしかすると当時懇意にしていた用品屋が長期在庫品とか展示品や新古品を安く譲ってくれたのかもしれない。
無論、「墨磨職人」のはたらきぶりや稼働時間から見れば十分安いものであることに変わりはない。必要な時期が来たら新しいものを調達することを考えなければならない。
